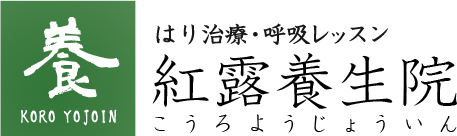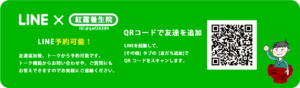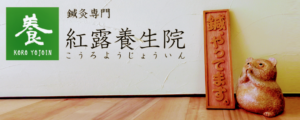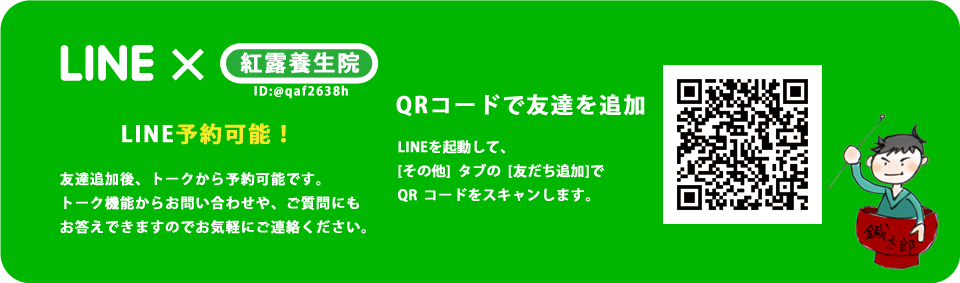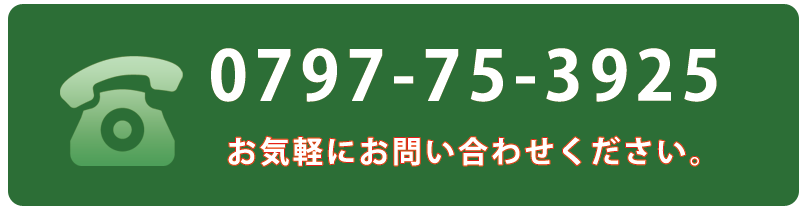ブログ
年間鍼灸受診率5%から50%の世界へ向けて
整動協会が提示する2つのイノベーション
先週末私が所属する整動協会が主催する経営サミットに参加してきました。
6名の役員の方々が毎週ミーティングを重ねて様々な情報を共有してくれていますので、こちらも相応の熱量で臨むことができ、整動鍼や活法セミナーを受けられたことがない鍼灸師の方々にも熱量が伝染する程の非常に活気付いたサミットになりました。
予想を遥かに超えてくる内容に、改めて感謝しております。
早速ですが、これは何の数字か分かりますでしょうか。
・5%/年
・5%/日
同じ5%という数字ですが上は国民が1年間に鍼灸院を受診した比率で、下は1日に国民が病院を利用する比率です。
国民1億人としても、1日に500万人が病院を利用するといわれる現状を皆さんはどうお考えでしょうか。
6名の講師全員が貴重な講義をしてくださいましたが、そのなかで年間鍼灸受診率5%から50%に普及していくための2つのイノベーションをこのブログで共有したいと思います。
患者さんの「目」をつくる
今回経営サミットというタイトルですが、ただ自院の集客が上がればという次元の話ではありません。
念頭には常に「患者さんのために」私たち鍼灸師が今取り組むべきことは何かというテーマがあります。
ここで我々が今取り組むべきことは、統一された規格を持って
選択肢と判断材料を提供し、患者さんの「目」をつくること
よく病院や鍼灸院などの医療機関や、整体院などの民間療法が使いがちな言葉が、「患者さん目線」という言葉です。
患者さん目線を再考した代表の言葉をシェアすると、必ずしも患者さん目線≠素人意見を大事にするではないということです。
9500万人の患者さんは鍼灸に効果があるかも、どんなことをされるか、どこに鍼を何本されるかも分かりません。
これは国民の大半が頼る病院にも同じことがいえます。
現状何か症状を患った方々は、適切な判断や選択ができていない方が大半です。
身内や知人に言われるがまま取り敢えず病院に行き、先生に言われるがまま取り敢えず画像診断・血液検査を受け、言われたから取り敢えず薬を飲む・検査入院をする。
自分の身体にも関わらず、自分の身体と全くコミュニケーションを取らずに他人に決められている傾向があります。
何も知らない患者さんにまずは病院へ、口コミが良いから鍼灸院へなどと促すのは決して患者さん目線ではなく、情報提供でもなく勧誘に近いかもしれません。
まずは提供する側が患者さんに、この場所では何ができるのかという内容を開示し、患者さん自身に選択してもらう必要があります。
再び代表の言葉を借りると、本当の患者さん目線はこう言えるのではないでしょうか。
目(判断に必要な知識)をもつ患者さんの視点から見えるもの
そのために我々鍼灸師側はある程度共通したルールを持ち、患者さんの「目」を育てていきたい。
患者さんが安心して鍼灸という治療法を選択肢の一つとして選べるような社会をつくっていくことが、何より症状によって孤独で苦しむ患者さんのためになると信じています。
信用と信頼の無限ループをつくる
もう一つ経営サミットらしく、集客の本質が隠れている信用と信頼の違いについても非常に興味深い内容でした。
信用(対象)がないと患者さんが集まりません。
信頼(関係)がないと仕事が続けられません。
信用は一方向で、信頼は双方向
集客という面を考えると病院は大変有利です。
国が7割引以上のチケットを無条件で国民に配り、TVやメディアはなにかあれば病院へという意識を常に植えつけてくれるので、病院は無条件に国民に信用されています。
後は来院された患者さんと信頼関係を構築することに注力できます。
当たり前のことを当たり前にすれば、結果に関わらず患者さんは通ってくれるのに、それさえもできない病院が多いのは、信用を得るための集客に頭や時間を費やしていないからだと思います。
ここを念頭に運営・従事されている方々が本来の医療従事者だと私は考えます。
私たち鍼灸師はどうでしょうか。
年間5%の受診率が表している通り、信用があるとはいえないのが現状です。
逆に来院された患者さんとの信頼関係は、できやすいとも言えます。
ではなぜ鍼灸業界がいつまでたっても信用を得れないかというと、鍼灸師一人一人がバラバラに信用と信頼を同時に得ようと頑張ってしまっているからです。
整動協会では、信用は組織で信頼は個人で得ていく方針が固まりました。
信用を得るためのエビデンスや統一された規格はすでに構築済みで、進行し続けています。
鍼灸師が内側から変わらないと、時代は変わらない
今回のサミットの熱量を肌で感じると、必ず国や医療業界、患者さんにとって有益なものになると確信しております。
前回のブログでも記載したように、実際に北海道では病院との共存が実現し、この流れが全国に広がっていく予定です。
誰得の視点がこれまで以上に患者さんに向けられる日はそう遠くないはずです。
当院ではこの取り組みに引き続き全力で関わっていきたいと思います。